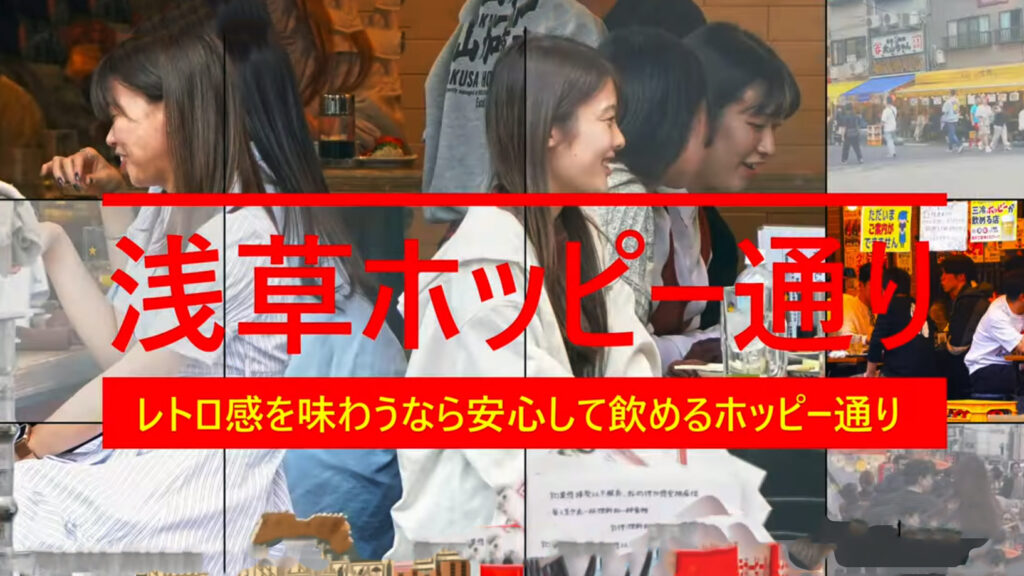水戸は水戸黄門で持つ
| 水戸駅は常磐線で東京駅から特急なら1時間半足らずで着いてしまう茨城県の県庁所在地で、1889年 (明治22年) 4月ついたちに市政施行されています。 |
| 水戸は、御三家の一つ水戸徳川家所縁の地であり、水戸黄門、(徳川光圀)や偕楽園で知られています。 |
| 毎年2月には水戸の梅まつりが行われ多くの観光客でにぎわいます。 |
| そして、8月には水戸黄門まつり、9月には水戸萩まつりが開催されます。 |
| 明治時代以降は納豆(水戸納豆)の生産が盛んになり、今でも皆さんの食卓にのぼることも多いでしょう。 |
| それでは水戸駅のコンコースから見ていきましょう。 |
| まず、なんといってもここで必ず寄ってほしいのは、水戸駅のみどりの窓口の横ある立ち飲みスタンド「いばらき地酒バー」、です。 |
| 前に来たときは、ミルクスタンドに併設されており、規模もしょぼい立ち飲み屋くらいでした。 その時は日本酒3種を『乾燥納豆』、をつまみに飲んだ記憶があります。 |
| 今回来てみるとみどりの窓口の隣に立派な店舗となっていました。 2022年にみどりの窓口横に移転したようです。 |
| 水戸駅を利用する茨城県内外の多くの人々に茨城県産地酒の魅力を伝えるため、立ち飲みスタンド「いばらき地酒バー」、の役割は大きそうです。 |
| 茨城県の地酒の試飲に加えて、地酒と笠間焼の酒器の販売もしています。 |
| 予算を消化するお役所仕事ではなくしっかり、水戸の地場産業を応援しているいい企画です。 |
| 『いばらき地酒バー』に出張や観光に来て帰り際に、水戸駅で電車を待つ間に軽く一杯ひっかけるのに最高です。 |
| 店内にある「茨城地酒サーバー」では、おちょこ1杯分を300円で楽しむことができますので、ちょっとした空き時間で日本所を味わうにはお手ごろですね。 |
| オススメは「地酒呑みくらべおつまみセット」で、好きな地酒を3種類と、日替わりで3品のおつまみがついたお得なセットです。呑み比べてみるとそれぞれの地酒の違いがわかりますので是非飲み比べてください。 |
| 水戸駅の駅ビルは『エクセル』というようです。さまざまな商業施設や飲食店がここに集中しています。 |
| コンコースには何処の駅でも見られるような同じようなお店と、地域の特産品を販売しているお店が並んでいます。 |
| 水戸駅北口を出ると水戸黄門様の像があります。テレビドラマで放映されていたので、年配の方なら見ていた方も多いのではないでしょうか。 |
| みとこうもんとは、江戸時代の水戸藩主である徳川光圀の別称で、徳川光圀が隠居してから日本各地を漫遊して世直しをしたという創作物語の名称であり、事実とは異なります。 |
| 実在の水戸藩主である徳川光圀は、国史編纂『大日本史』の為に史局員の儒学者らを日本各地へ派遣して史料蒐集を行っていますが、光圀自身は鎌倉遊歴と、藩主時代に江戸と国元の往復や領内巡検をしている程度で、諸国を漫遊したという記録は確認されていません。 |
| 光圀は同時代の伝記資料において名君と評され、庶民の間でも知名度は高かったようです。亡くなった時には、「天が下 二つの宝つきはてぬ 佐渡の金山 水戸の黄門」という狂歌が流行ったほどです。 水戸黄門漫遊譚の成立には、この様な名君としての評判や、幕末における水戸学の浸透が後の物語の形成に影響していると思われます。 |
| 光圀の伝記資料としては、正伝である『義公行実』をはじめ『桃源遺事』『久夢日記』など様々なものがあり、宝暦年間にはこれらの伝記資料を基に実録小説である『水戸黄門仁徳録』が成立し、黄門漫遊譚の起源となっています。 |
| また史実の光圀は、家臣の佐々十竹らを各地へ派遣しており、彰考館総裁であった佐々とあさかたんぱく、の二人が、後の助さんと格さんのモデルと思われます。 |
| 水戸黄門の名は、光圀が徳川御三家の一統である水戸藩の藩主であり、武家官位として権中納言を名乗っていたことから、「徳川光圀」と直言することを避けるために、藩名である「水戸」と、中納言の唐名である「黄門」をとって別称として『水戸黄門』と名乗られたようです。 |
| 講談の『水戸黄門漫遊記』は幕末になって、講談師がこれらの伝記や十返舎一九作の滑稽話『東海道中膝栗毛』などを参考にして『水戸黄門漫遊記』を創作したと考えられています。 |
| 内容は、「天下の副将軍」こと光圀がお供の俳人を連れて諸国を漫遊して世直しをするというもので、大変な人気作となりました。徳川幕府の職制に副将軍職はありませんが、水戸徳川家には参勤交代がなく江戸定府であったことから、家臣の中には 「いったん将軍にことあるときは、水戸家当主が代わって将軍職を務める」と思いこんで「副将軍」という者もいたといいます。 この講談話の始まりについては、一橋慶喜を将軍職に就けるため、父である水戸斉昭が裏で動いて、水戸徳川家は「天下の副将軍」 であるという話を世間に広めようとしたのだという説もあります。 |
| 明治になると、大阪の講釈師玉田玉知がお供を俳人ではなく家臣の佐々木助三郎と渥美格之進の二人とする話に膨らませています。 さらに人気の題材となっていった。助さん、格さんは、『東海道中膝栗毛』の「弥次さん、喜多さん」のキャラクターを参考にしたのかもしれません。 明治初期の黄門物の講談は東京と大阪では演じられるすとーりーが異なっていましたが、助さん、格さんを従えた大阪のストーリーが主流になっていったようです。 |
| 徳川幕府が衰退した幕末から維新後の明治、大正、昭和の第二次世界大戦前にかけて、江戸時代と比べ徳川氏への評価が著しく低下しましたが、水戸黄門の物語はにんきでした。 この背景には、実在の光圀が天皇を敬ったり楠木正成を忠臣として称えたりして、『大日本史』編纂や水戸学が尊王論や天皇制、南朝正閏論に多大な影響を及ぼしていることと関係していると思われます。 幕末から戦前の水戸黄門の講談や小説などでは、湊川神社へ楠木正成の墓参に行くなどの尊王論的色彩が強かっようです。 大戦後の映画やテレビドラマではそのような尊王色は払拭されていきました。 |
| 明治末期に日本でも映画製作が始まると、時代劇映画の定番として『水戸黄門漫遊記』も、もてはやされ、戦前から戦後にかけて多くの映画作品が制作されました。時代劇の大スターたちが水戸黄門役を演じています。 |
| 戦後は占領期の剣劇禁止を経た後に、東映が市川右太衛門に続いて月形龍之介を主演にシリーズ化しました。 初期の月形黄門はB級作品でしたが、好評のためオールスターキャストの大作が作られるようになり、題名も従来の『水戸黄門漫遊記』から単に『水戸黄門』となっていった。 |
| そして映画時代からテレビ時代になると、TBSが月形を主演にブラザー劇場にてテレビドラマ化した。 |
| さらに月形と同様に悪役が多かった東野英治郎を主演に起用したナショナル劇場(のちのパナソニック ドラマシアター、以下同じ)シリーズ『水戸黄門』は更なる人気を博し、黄門ほか数役の俳優を幾たびか変更しつつ長寿番組となりました。 レギュラー番組としては2011年12月まで続きました。 このナショナル劇場版では脚本家の宮川一郎の案により、ドラマの毎回の佳境で三つ葉葵の紋所(徳川氏の家紋)が描かれた印籠を悪人どもに見せて 「この紋所が目に入らぬか」と水戸黄門の正体を明かすという筋書きとなりました。 |
| 作品中、光圀が越後のちりめん問屋(ちりめん問屋「越後屋」)の隠居・光右衛門と名乗る設定、助・格が印籠を悪人に見せるクライマックス、物語の冒頭で家老の中山備前・山野辺兵庫らが、出立しようとする光圀一行を諫めるシーン、さらには一行に護衛(密偵)の忍者(風車の弥七、霞のお新、かげろうお銀・疾風のお娟、柘植の飛猿など)が加わるなど物語は膨らまされていきました。 それは、テレビドラマ『水戸黄門』での演出でした。 その他の水戸黄門作品の共通の設定ではありません。 |
| あらすじは、時は元禄、「犬公方」こと五代将軍徳川綱吉が収める時代でした。 隠居した光圀はお供の俳人を連れて、諸国漫遊を兼ねて藩政視察の世直しの旅に出かけます。 悪政を行なう大名や代官などがいれば、光圀は自らの俳号「みずかくし梅里」を書き記すなどしてその正体をほのめかし、悪政をただしました。 しかしながら光圀が正すのは役人の不正であり、時には身分制度の掟で結ばれない恋人同士に粋なはからいを示すことなどはあったようですが、実在の人物であることと、あくまで隠居の身であるため大々的に社会改革にまで踏み込もうとする展開はありません。 |
| お供は明治の講談以降、佐々木助三郎と渥美格之進の二人に定まりました。 TBSのテレビドラマ版では世直し自体を目的として旅立つというよりは、シーズンごとに陰謀やお家騒動といった主軸のストーリーがあり、その解決のため目的地に赴く途中で、出会った人々を成り行きで助けるというサブストーリーが毎回展開される構成が定番となっていました。 |
| 水戸というとやっぱり誰もが思い浮かべる『水戸黄門』の話を中心に語ってきました。 このような背景を知ったうえで水戸黄門を見るとまた面白いかもしれません。 |
水戸で泊まるホテル
-



【動画】逮捕されたFC2に動画がある木村雪乃さん、ガチで可愛い😍
-



身に覚えのない商品が送られてきた
-



【必要】お医者さんへの謝礼・心付けは絶対に渡して。相場は3~50万円。研修医は1~3万😉
-



【悲報】大阪・豊中市の学校給食が「少なすぎる」と物議😋
-



【悲報】ベトナム人実習生さん、日本に失望してしまう😥
-


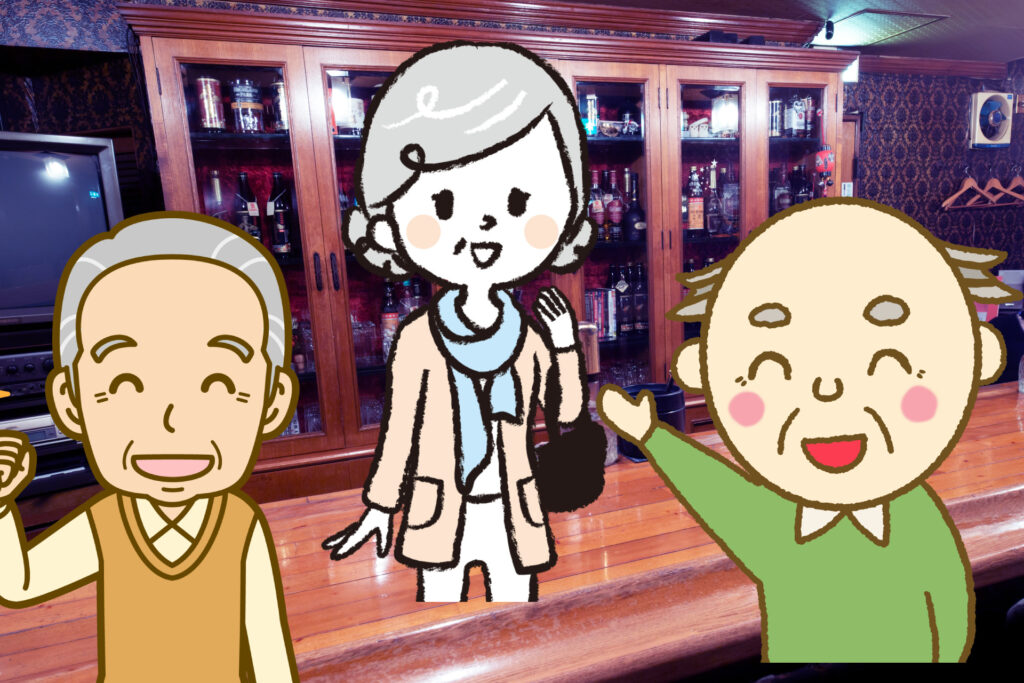
【高齢化社会】66歳と80歳のジジィが70代女性を取りあって喧嘩🤣
-



落ちるなよ…落ちるなよ…落ちたーギャハハ(≧▽≦) ⇒ 皇室案件となる
-


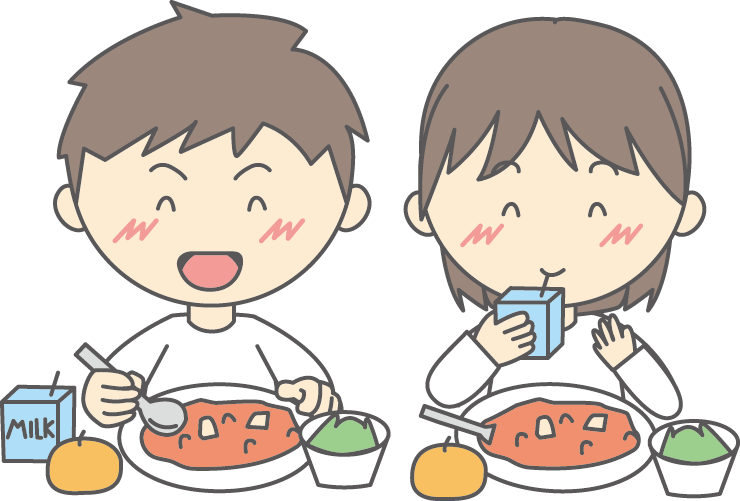
【悲報】川崎市の小学校さん、子供たちに刑務所以下の給食を提供してしまう😢
-



【朗報】マイナンバーカードと外国人在留カード一体化へ 外国人の不正が困難に😃
-



【絶滅危機】ゴキブリ、35℃以下でしか生存できないポンコツだった🤣